「花粉症」今年は早い傾向
こんにちは、漢方なつめの福山です^^
先日2月号の「なつめ通信」を投函しました。当店がオープンしてから2ヶ月に1度を目標に作成してきたのですが、今回で40号を迎えました。お客様に「読んだよ」と声をかけていただくことが嬉しく続けています。ありがとうございます。今回は「花粉症・抗アレルギー薬を漢方薬はどう使い分ける?」など花粉症の内容を中心とした記事になります。ぜひご一読くださいませ。
花粉症の漢方治療についてですが、大きくは対処療法と根本治療に分かれます。対処療法の漢方の方が有名でご存知の方も多いかも知れません。
一番多い症状の「水のような鼻水が出る」という時は小青竜湯や麻黄附子細辛湯を使います。症状が軽いときは小青竜湯だけで良いですが、それでも止まらない場合は麻黄附子細辛湯を合わせると止まりやすくなります。鼻詰まりや副鼻腔炎などの症状に対しては、辛夷清肺湯や頂調顆粒などを使います。副鼻腔炎までの症状がある場合は、ケースバイケースなのでご相談いただけると嬉しいです。鼻水の色ですとか、咳があるかどうか、頭痛があるかどうか、後鼻漏の症状などで処方の内容が変わりますので、ご相談ください。
根本治療はといいますと、中医学でいうと「衛気」を強くすることが大切です。体を防衛する気のことで、わかりやすく言うと粘膜のようなイメージです。この「衛気」が弱くなると、風邪にかかりやすくなったり、花粉、ほこりなどのアレルゲンに反応しやすくなります。季節の変わり目に皮膚が敏感になったりするのもその影響です。
この「衛気」を強くしてくれるのが、黄耆を使った「衛益顆粒」です。根本治療となるのでシーズンに入る前からコツコツと飲むことが大切です。(現代人で、衛益顆粒が必要な人はとても多いと思うのですよね。)
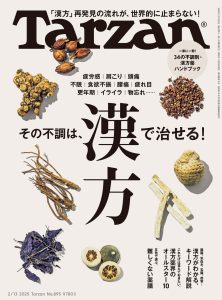
※「TARZAN」2月号の漢方特集で、アレルギー性鼻炎の根本治療として衛益顆粒が紹介されています。
食養生もとても大切です。花粉症などのアレルギーは「肺」「脾」「腎」の3つが原因と考えられています。この中で、特に食養生によって改善しやすいのが「脾」の部分です。脾は、消化器系の胃腸をさし、胃腸が弱いと水分の代謝がうまくいかず、水が溜まる「痰飲(タンイン)」が生じて、くしゃみ、鼻水や痰が出やすくなります。さらに「脾胃」が疲れると体を防御する「衛気」が作られなくなり、粘膜も弱くなります。
具体的には、①小麦を控える②乳製品、冷たいものを控える③砂糖を控えると良いでしょう。こう聞くと難しいと思われるかも知れませんが、朝ごはんを和食にするだけでもだいぶ違います。漬物や味噌汁などの発酵食品も摂ることができます。

舌を見て、苔が厚い時は胃腸が疲れて水が溜まっているサインです。鏡を見ながら苔が取れるようにあっりとしたものを食べると良いでしょう。
今年は夏が暑かった影響でスギの花芽が早く成長し、花粉の飛散も例年より早いようです。つらい花粉シーズンですが、漢方薬を取り入れたり、食事に気をつけながら、少しでも快適にお過ごしください。